短い散歩でも、足元に目を向ければ小さな命の営みを発見できます。畦道(あぜみち)で跳ねるカエル、草むらを飛び交うトンボ、庭先に遊びにくるチョウやテントウムシ…。山武市の自然には、子どもからお年寄りまで誰もが触れ合えるたくさんの生きものが暮らしています。私たちはこの豊かな自然環境と生きものたちに日々支えられ、癒やされながら暮らしているのです。
生物多様性ってなに?
■ 生物多様性ってなに?
生物多様性ってなに?
生物多様性(せいぶつたようせい)とは、地球上に様々な種類の生きものがいて、それぞれが関わり合いながら生きていることを指します。森や海、川、里山といった多様な環境に無数の生物が存在し、さらに同じ種類の中にも遺伝的な違い(個性)がある――そんな「いろいろな命がある状態」が生物多様性です。
たとえるなら、地球という大きなクラスに、動物、植物、きのこ、微生物までみんなが一緒に暮らしているようなものです。名前も知らない小さな虫や土の中の微生物も含め、すべての生きものが互いにつながり支え合っているのです。山武市の自然も、この地球全体の生物多様性の一部であり、大切な仲間です。
なぜ生物多様性を守ることが大切なの?
■ なぜ生物多様性を守ることが大切なの?
なぜ生物多様性を守ることが大切なの?
私たち人間は生物多様性の恩恵(おんけい)をたくさん受けています。生きものが豊かに存在することで成り立つ暮らしや文化があり、生物多様性が失われるとその恩恵も失われてしまいます。主な理由を見てみましょう。
1. いのちのネットワークを支えるため
動物も植物も虫も、みんな食物連鎖などでつながった命のネットワークの一部です。一種類でも欠けてしまうと、蜘蛛の巣の糸が切れるようにバランスが崩れてしまいます。たとえば、小さな昆虫が減ってしまうと花粉を運ぶことができず、野菜や果物が実らなくなって私たちの食卓にも影響が出ます。生物多様性を守ることは、この命のネットワークを守ることなのです。
2. 私たちの安全と健康のため
森は「天然のダム」と呼ばれます。木々が雨水をたっぷりと吸い込み、洪水や土砂崩れを防いでくれるおかげで、安全に暮らせます 。また、私たちの薬のもとになる植物の多くは野生に由来しています。森に自生する薬草が失われれば、将来の新しい薬を得られないかもしれません。生物多様性は私たち自身の健康や命を守る土台でもあります。
3. 豊かな地域の恵み(経済)のため
自然がもたらす恩恵は経済的な価値も大きいです。農業や漁業で収穫できる作物や魚、林業で得られる木材、観光客を惹きつける美しい景観――いずれも生物多様性があってこその地域の財産です。山武市でも、新鮮な野菜やお米、美しい海と砂浜、豊かな緑があるからこそ人が集まり、仕事が生まれています。自然を守ることは、地域経済の基盤を守ることにもつながります。
4. 心と文化を豊かにするため
私たちの暮らしの中で、自然は季節を感じさせる行事や文化を育んできました。春の桜の開花、夏のホタルの舞、秋の紅葉、冬の渡り鳥の飛来――そうした季節の風物詩があるからこそ、歌や思い出が生まれ、心が豊かになります。もし自然が失われてしまったら、私たちの思い出や地域の文化も色あせてしまうでしょう。生物多様性を守ることは、未来の子どもたちに美しい景色と思い出を手渡すことでもあります。
このように、生物多様性は私たちの生活や社会のあらゆる面を支えてくれている大切な基盤です。その豊かさを失わないように守っていくことが、私たち自身のためでもあり、未来への責任でもあります。
生物多様性が失われるのはどんなとき?
■ 生物多様性が失われるのはどんなとき?
生物多様性が失われるのはどんなとき?
便利で豊かな暮らしを追求する中で、私たちは気づかぬうちに生物多様性を脅かしてしまうことがあります。どんな人間の活動が自然環境に影響を与えているのか、いくつか見てみましょう。
- 森を切りすぎること(森林伐採): 家を建てたり紙を作ったりするために必要以上に木を伐(き)ってしまうと、森そのものが減ってしまいます。森が減れば、そこに住む動物たちの住みかも失われ、生態系のバランスが崩れてしまいます 。
- ものを作りすぎ・使い捨てすぎ(大量生産・大量消費): 私たちが服や道具を次々と買い替えて大量に消費すると、その生産過程で大量のエネルギーや水が使われ、CO₂や廃棄物が発生します。必要以上の消費は地球の資源をどんどん減らし、環境汚染の原因にもなります。
- プラスチックごみの問題: 便利なプラスチック製品も、使い捨てのものが川や海に流れ出ると生きものに深刻な被害を与えます。例えば、海に漂うビニール袋をウミガメがクラゲと間違えて食べてしまったり、海鳥がプラスチックの破片をのみこんで命を落とすことがあります。身近なごみも生態系に影響を及ぼしているのです。
- 気候変動(地球温暖化): 車や工場から出るCO₂などによって地球の気温が上がると、世界規模で生態系に変化が起きます。気候変動は私たちの暮らしにも影響し、台風や大雨など異常気象が増えると田畑や沿岸部の自然も被害を受けてしまいます。
- 里山離れ(利用しなくなること): 山武市を含む日本各地の里山では、昔に比べ人の手が入らなくなったことで環境が変わってきています。かつては薪(まき)を集めたり落ち葉を肥料にしたりして手入れしていた森も、人が使わなくなると竹や雑草が生い茂り、明るかった林は暗くうっそうとした茂みへと変わります。こうして放置された里山では、本来住んでいた動植物が暮らしにくくなり、生物多様性が低下してしまうのです。
このように、人間の活動が原因で自然環境が壊れてしまうと、その場所に生きる生きものだけでなく巡り巡って私たちの生活にも影響が及びます。しかし裏を返せば、人間の工夫や行動次第で生物多様性を守ることもできるということです。では、私たちにどんなことができるでしょうか?
里山をみんなで育てよう:失われつつある身近な自然を守るために
■ 里山をみんなで育てよう:失われつつある身近な自然を守るために
里山をみんなで育てよう:失われつつある身近な自然を守るために
山武市のように豊かな里山や田畑がある地域では、「里山を守ること」が生物多様性を守ることにつながります。里山とは人里近くの山や森で、人と自然が共に生きる場です。昔からこの地域の人々は里山から薪や山菜を得て、田畑では稲作や野菜作りをしながら自然と寄り添って暮らしてきました。里山の落ち葉は畑の肥料となり、森から湧き出るきれいな水は川となって田んぼを潤し、そこにホタルやメダカが生息する――そんな循環が保たれていたのです。
しかし近年、生活様式の変化により里山の環境は大きく変わりました。安い食べ物や木材を遠くから運んで買えるようになり、ガスや電気の普及で薪を使わなくなり、化学肥料が広まって落ち葉など自然の恵みを利用する機会も減りました。さらに都市への人口流出で里山を世話する人手も減っています。その結果、手入れされなくなった里山は荒れ、竹林が増えたり森が密集しすぎたりして、多様な生きものが暮らしにくい環境になってしまっています。
里山を元気にするためには、「地産地消」の力が重要です。「地産地消(ちさんちしょう)」とは、その土地で生産されたものをその土地で消費すること。例えば山武市で採れた新鮮な野菜やお米を地元で食べたり、市内の森の木材を地域の建築や家具に使ったりすることです。地産地消が進むと、私たちの暮らしと里山がもう一度しっかりつながり、生きものに優しい循環が生まれます。地産地消によって里山が元気になる理由を整理してみましょう。
- 里山の資源に価値が生まれる: 地元の木や農産物を使うことで「この森や畑は役に立っているんだ」と価値が見直されます。使われなくなっていた山の木を間伐(かんばつ)すれば森に光が差し込み、多様な植物が育ちやすくなります。
- 地域にお金や仕事が回る: 地元の産物を買うとお金が地域に留まり、林業や農業など関連する仕事が増えます。若い人も地元で働く機会ができれば、里山の管理に携わる人も増えていきます。
- 環境にやさしい: 遠くから輸送する量が減るため、トラックや船で出るCO₂の排出を減らすことができます。また、里山の恵みを活かす暮らしは化石燃料や化学肥料の使用を減らし、環境負荷が小さくなります。
- 人と人、生きものがつながる: 地元の生産者と消費者が顔見知りになり、「このお米はあの農家さんが作ったんだ」とわかるようになります 。そうした関係性は地域の絆(きずな)を深め、みんなで自然を大切にしようという気持ちを育みます。里山と人とのつながりが戻れば、森の中の生きもの調査やホタル復活プロジェクトなど共同の取り組みも活発になります。
山武市でも直売所での地元野菜の販売や、地域の森林ボランティア活動など、少しずつ地産地消・地域循環の取り組みが広がっています。私たち一人ひとりが地元の自然の恵みを積極的に利用し、大切にすることが、里山の再生につながり、生物多様性を守る力になります。
私たちにできることから始めよう
■ 私たちにできることから始めよう
私たちにできることから始めよう
生物多様性を守るために必要なのは、決して特別なことではありません。身近な暮らしの中での小さな工夫や、地域の活動への参加といった誰にでもできる一歩の積み重ねが、大きな力になります。今日からできること、これから挑戦してみたいことをいくつか挙げてみます。
- 日々の暮らしで自然に配慮する: 必要な分だけ物を買い、使い捨てを減らしましょう。マイバッグやマイボトルを持ち歩き、ゴミの分別やリサイクルを心がけるだけでも、資源の無駄遣いや自然への負荷を減らせます。電気や水を大切に使い、車より自転車や公共交通を利用すれば、温室効果ガスの削減にもつながります。
- 自然を感じて楽しむ: 家の近くの林や海辺を散策(さんさく)してみましょう。季節ごとに姿を変える草花や、生きものたちの声に耳をすませてみてください。里山を歩けば、木漏れ日(こもれび)の下で鳥の声や虫の音が交響し、自然の豊かさを肌で感じられます。身近な公園や森で開催される自然観察会に参加するのもおすすめです。まずは自然を好きになること、それが守る第一歩です。
- 地域の活動に参加する: 身近なところで行われている環境活動にぜひ参加してみましょう。例えば、山武市では地域有志による清掃活動や里山の下草刈り・植樹(しょくじゅ)活動、子ども向けの農業体験イベントなどが行われています。海岸のゴミ拾いに家族で参加すれば、楽しみながら浜辺をキレイにできます。みんなで汗を流して里山を整備すれば、ホタルが飛び交う水辺や希少な野草が咲く森を未来に残すことができます。(さんむほたる プロジェクトが2025年から始まりました)最初は見知らぬ人同士でも、「自然が好き」という共通点ですぐに打ち解け、地域の輪に溶け込めるでしょう。
- 地産地消を実践する: 買い物の際はなるべく地元産の食品や製品を選んでみましょう。山武市の直売所や朝市には、新鮮な野菜やお米、採れたての魚介などが並びます。旬の地元産を味わうことは、地域の農家さんや漁師さんを応援することにもなります。お店で「このお野菜はどこで採れたのですか?」と尋ねてみたり、地元のお祭りで特産品を味わったりするのも良いですね。地元の材木で作られた木工品や伝統工芸の製品を日常に取り入れることも立派な地産地消です。身の回りから少しずつ地産地消を意識してみましょう。
こうした一つひとつの行動は小さいかもしれませんが、生物多様性を守るための確かな一歩です。特別な知識や技能がなくても、できることから始めれば大丈夫。大切なのは、それを継続することと周りに伝えることです。「ホタルが見られてうれしかった」「海岸のゴミ拾いで達成感があった」など、感じたことを家族や友人に話したり、写真や絵日記に残したりすれば、その想いがまた周りの人を動かす力になります。
豊かな自然を未来へつなごう
■ 豊かな自然を未来へつなごう
豊かな自然を未来へつなごう
生物多様性を守ることは、山武市という私たちのふるさとの自然を守ること、ひいては地球全体の未来を守ることにつながります。今、私たちが享受している森や海の恵み、美しい景色は、先人たちが守り伝えてきてくれたものです。次は私たちの番として、この豊かな里山や海辺の自然を子どもや孫の世代へ引き継いでいきましょう。
一人ひとりの力は小さく見えても、集まれば大きな力になります。身近なことから行動を起こし、それを周囲に広げていくことで地域全体が変わっていきます。そして、地域の取り組みが積み重なれば、やがてそれは地球規模の自然保護の力にもなっていくのです。山武市の美しい里山とそこに息づく生きものたちを守るため、今日からできることを始めてみませんか?
- 地元で採れたものをいただき、旬の味を楽しみましょう。
- 自然の中を散策し、生きものたちとのふれあいを楽しみましょう。
- 心動かされた自然の風景は、写真や絵、文章に残して周りに伝えてみましょう。
- 生きものや自然、人や文化のつながりを守るため、地域の清掃活動や里山保全の取組に参加しましょう。
何気ないこれらの行動が、生物多様性を守る大きな力になります。豊かな里山をみんなで育てながら、生きものと共に生きる未来を築いていきましょう。里山をみんなで育てながら、生物多様性を守っていきましょう!









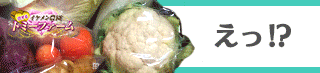






















奥千葉 山武市を中心に 自然栽培を中心に、ネイチャーポジティブと無農薬栽培での地域活性化を目出しています。