節分とは
■ 節分とは
節分とは
四季の始まりの前日のことを節分といい、季節を分ける日、つまり立春・立夏・立秋・立冬の前日です。
2月3日だけじゃないんですよ。
ではなぜ、立春を重要な日としたのか。
「立春正月」とも言われ、年の始まりの前日とし、大晦日として重要な日とされていました。
豆まきはなぜ始まったのか
■ 豆まきはなぜ始まったのか
豆まきはなぜ始まったのか
邪気を追い払うために、節分には古くから豆撒きの行事が執り行われている。宇多天皇の時代に、鞍馬山の鬼が出て来て都を荒らすのを、祈祷をし鬼の穴を封じて、三石三升の炒り豆(大豆)で鬼の目を打ちつぶし、災厄を逃れたという故事伝説が始まりと言われる[2]。豆は、「穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっている」という信仰、または語呂合わせで「魔目(豆・まめ)」を鬼の目に投げつけて鬼を滅する「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより、邪気を追い払い、一年の無病息災を願うという意味合いがある。
と言う説がありますが、中国の習俗から伝わってきたとも言われています。
「鬼は内」と言うところがあるって知っていますか?
■ 「鬼は内」と言うところがあるって知っていますか?
「鬼は内」と言うところがあるって知っていますか?
「福は内、鬼は外」と豆まきしましよね?
鬼を祀っているお寺さんでは「鬼は内」という言うそうです。
節分 に お蕎麦(そば)を食べる 地域 由来
■ 節分 に お蕎麦(そば)を食べる 地域 由来
節分 に お蕎麦(そば)を食べる 地域 由来
節分にお蕎麦を食べる風習は江戸時代からありました。
昔は節分に食べるお蕎麦を年越しそばといい、立春の前日である節分に食べていたそうです。
蕎麦の実は魔除けになると言われ、蕎麦を食べることで邪気を追い払っていました。
今でも節分にお蕎麦を食べる地域は存在しています。
節分に柊鰯(ひいらぎいわし)を飾る 地域
■ 節分に柊鰯(ひいらぎいわし)を飾る 地域
節分に柊鰯(ひいらぎいわし)を飾る 地域
西日本では、「焼嗅(やいかがし)」とも呼ばれるそうです。
鬼は臭いもの、尖ったものが嫌いとされていて、鬼の侵入を防ぐために飾るそうです。
またイワシを食べる習慣もあるそうです。
柊鰯は平安時代までさかのぼり、土佐日記に
「小家の門の端出之縄(しりくべなは)の鯔(なよし)の頭、柊らいかにぞ。とぞいひあへなる」
と記されています。
節分に恵方巻を食べる 地域
■ 節分に恵方巻を食べる 地域
節分に恵方巻を食べる 地域
恵方巻は全国的に定着してきましたよね?
七福神にあやかり7品の具を巻いた太巻きを恵方の方向を向いて無言で食べます。
恵方とは、その年の幸福を司る歳徳神のいる方角のことで、2016年は、南南東です。
節分に落花生をまく 地域
■ 節分に落花生をまく 地域
節分に落花生をまく 地域
北海道、東北、信越地方の8割の家で落花生をまくことが定着しています。
昭和30年代に北海道で始まったそうです。
歴史があるんですね。
開拓文化の北海道の人たちは「食べ物を粗末にしない」、「大豆よりカロリーが高い」と言った雪深い地方だからこそ考えられたそうです。それが東北、信州へと広がり、今では関東でも節分の時期になると大豆と一緒に並ぶようになりました。
節分にクジラを食べる 地域
■ 節分にクジラを食べる 地域
節分にクジラを食べる 地域
山口ではクジラを食べるそうです。
クジラを食べることで「大きな幸せ」を祈るそうです。
節分にこんにゃくを食べる 地域
■ 節分にこんにゃくを食べる 地域
節分にこんにゃくを食べる 地域
四国地方ちゅうしんに節分にこんにゃくを食べる風習があるそうです。
「砂おろし」といって体内にたまった砂を出す、つまり腸の中を掃除する意味があります。
しもつかれ
■ しもつかれ
しもつかれ
栃木の郷土料理、「しもつかれ」。
神社に供え、近所の方と分け合う伝統料理だそうです。
■
そばの由来
■ そばの由来
そばの由来
「そば」は「わき」や「かたわら」を意味する「側・傍」ではなく、「とがったもの」「物のかど」を意味する「稜」に由来する。
これは、植物のソバの実が三角卵形で、突起状になっていることからである。
実は乾くと黒褐色になることから、『和名抄』では「クロムギ」と称している。
食品としての「蕎麦」は、そば粉に熱湯を加えてかき混ぜた「そばがき」が、江戸時代以前には一般的であった。
江戸時代以降、現在のように細く切られるようになり、当初は「そばぎり」と呼ばれた。
まだまだ知られていない風習や習慣がありますよね?
うちは他の家と違う、そう思ったら調べてみてください。
きっとそこには訳があると思います。








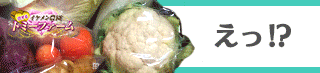





















食べることが好き。旅行することが好き。そんな私が各地見た、食べたをお伝えできたらと思っています。