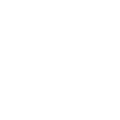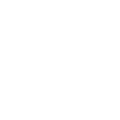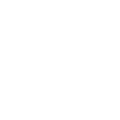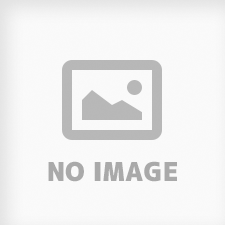花びらの絨毯
■ 花びらの絨毯
花びらの絨毯
おだやかな陽射しが、つぎつぎ舞い落ちる花びらをきらきらと光らせていた。
商店街から一本裏にある、小さな川べりのお散歩コースは普段は人影もないけれど、桜の季節だけは街の主役とばかりに華やいでいる。子供もお年寄りもサラリーマンも、まるでみんな昔からの顔見知りのように微笑みながら桜並木の下を通り過ぎていく。
私はすぐ目の前を歩いている彼と、きっちり距離を保ったまま歩いていた。
お惣菜やらお肉やらが入ったスーパーの袋が、私たちの手元で一つずつ、カサカサと音を立てながら終始無言のふたりをかろうじてつないでくれている。
満開をすぎた花びらが、彼と私のあいだにつぎつぎと舞い落ちる。
ふたりでおなか抱えて笑ったのって、いつだっけ。
そんなことをふと考える。
足もとには一面の花びら。天気予報では明日は春の嵐が吹き荒れるとのこと。この桜色の絨毯もきっと吹き飛んでしまうだろう。桜もぜんぶ散ってしまって、すぐにこの川べりのこともみんな忘れてしまうのだろう。
何もなかったかのように。
あっという間に散っちゃうね。
私は心の中でつぶやいた。
「今晩、どっかで飯でも食うか」
彼の手元でカサカサと音を立てていたスーパーの袋が止まった。
ぼうっと歩いていたから、突然立ち止まった彼の背中にぶつかりそうになる。
「お惣菜買っちゃったじゃん」
「明日でいいよ」
彼はそう言うと、すっと私の手を取って、また歩き出した。私の数センチ前をリードして。
昨日の夜、私たちは喧嘩をした。
喧嘩といっても日常茶飯事、とるに足りない、夫婦喧嘩は犬も食わない、そんないつもの小さな言い争いだった。
気まずくしていたのは私のほうだった。
彼の手はとてもあたたかかった。
しっかりとした意思をもっていた。
彼のあたたかい心が、しっかりと私の手に、私の中に伝わってくる。
「きれいだね」
と彼は見上げた。
満開を過ぎた桜の花びらがつぎつぎと彼と私に舞い落ちる。
「あっという間に散っちゃうね」
と私が言うと、
「来年また見に来ればいいよ」
と言って、横顔のまま微笑んだ。
そう。
消えてなくなっちゃうんじゃない。
日常にかまけて、私が忘れてしまうだけなんだ。
あしたもあさっても、私が忘れなければいい。ただそれだけなのに。
この人の優しさも照れくささも強さも弱さもぜんぶ、大好きなんだ。
この大きな手から伝わってくる、この人のぜんぶが好きだったんだ。
なんでそんな大切なことを忘れてしまうんだろう。
いつだって、こうして私の横で、微笑んでくれるのに。
私たちの足もとからはどこまでも桜色の絨毯が伸びていた。
明日には春の嵐でぜんぶ吹き飛んでしまうかもしれない。
私は彼の手をしっかりと握り返した。